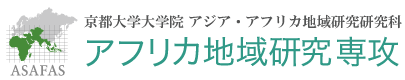*インタビュアー:I
I:最初に、太田先生の研究について教えていただけますか?
太田:わたしが今、興味をもってとり組んでいる研究テーマは、大きくわけると2つあります。ひとつは、わたしは東アフリカの牧畜社会の研究をずっと続けてきたのですが、この社会のなかで、家畜とカネとが、いったいどのような関係になっているのか、という問題です。もうひとつは、こうした牧畜社会にかぎらず、ひろくアフリカ社会全体で、紛争はどのようにして起こり、どのように解決されているのか、そして人びとが共生するかたちは、どのように構築できるのか、という課題です。
I:そのふたつのテーマのうち、まず、最初のものから説明していただけますか。

結婚式でのダンス(トゥルカナ)
太田:はい。東アフリカの牧畜社会では家畜がもっともたいせつな財産となっています。家畜は人間に食糧をあたえてくれるだけではなく、ほかにも大切な役割を果たしています。たとえば、人びとが結婚するときには「婚資」として家畜を支払います。家畜をもっていない人は結婚もできません。また、人びとは病気になったときにいろいろな治療方法を試みるのですが、たとえば占い師に相談すると「黒いヤギを殺して、その肉を煮たスープに薬を混ぜて飲み、その皮の一部を身につけなさい」などと言われることがあり、家畜がいないと病気の治療もできません。彼らの社会では重要な儀礼をおこなうときには必ず家畜が殺されます。つまり家畜は、結婚などによって新しい社会関係をつくったり、そうした関係を維持するために贈与・交換されるし、あるいは、カミに祈願するなど、宗教的にも重要な役割を果たしています。
そのために牧畜社会では、誰もが「たくさんの家畜をもちたい」と思っていますし、必要なときには、気前よく、その家畜をほかの人にも与えます。家畜は、もっとも重要な財産ですし、ほかのもの、たとえばモロコシやヒョウタンなどの農産物や、ナイフや槍などの鉄製品などと直接に交換されてきました。そうした意味で家畜は、わたしたちの社会におけるおカネと同じような役割を果たしていることがわかってもらえると思います。
I:おカネとおなじような機能をもつものは「自然貨幣」とか「原始貨幣」と呼ばれるものですか?貝の仲間とか、石や鯨の歯とか…。

水場でラクダに給水するトゥルカナの少女
太田:そのとおりです。家畜も原始貨幣のひとつとされてきました。けれども家畜とおカネとは、いくつかの点でおおきく異なっています。第一に、おカネは金属や紙でできていて、それ自体はあまり役にたちません。紙幣を燃やして暖をとるとか、コインをつなぎあわせて棍棒のかわりに使う、といった特殊な用法もあるかもしれませんが(笑)。しかし家畜の場合は、肉やミルクを供給してくれる。つまり、実際に役に立つ。これがおおきな違いです。
第二の重要なちがいは、家畜の一頭一頭が個体識別されていることです。牧畜社会の人びとは、自分の家族が所有している家畜はもちろんのこと、近い親族や隣人の家畜についても、詳細な知識をもっています。これは人間の顔を覚えるのと同じことで、一頭一頭について、その親がどれかとか、どこから来たかとかも知っています。
たとえば、「aさんが嫁入りしたときに、その夫が婚資としてaさんの母親に贈ったメスウシXがいた。そしてその後にXはYというオスウシを生んだ。あるとき、その家族の隣人のbさんの子どもが病気になり、病院代の支払いのために現金が必要になった。bさんは隣人であるaさんの母親に頼んで、Yを売却し、その代わりに彼女にメスウシZを与えた。そしてそのZが3番目に生んだ子どもが、このウシだ」といったような細かな来歴を、人びとは語ることができます。
I:すごく細かい知識なんですね!

少年の髪をととのえる姉(トゥルカナ)
太田:ええ、すごいでしょう!この人びとがとてもたくさんの、おそらくは千頭を超える家畜を個別に記憶していて、その来歴も知っていることには、調査をしていて、本当にびっくりさせられます。そして、人びとの人生のなかで起こった重要な出来事には、必ず何らかの具体的な家畜が関与しています。上の例では「婚資として支払われたXというウシ」「病気治療のために売却されたY」そして「それとの交換で入手したZ」が、それにあたります。こうした家畜の一頭一頭は、人びとがつむいでゆく「歴史の結節点」を構成している、その意味において、それぞれの家畜は、ほかの個体では代替できない、かけがえのない性質、つまり「単独性」をもっている、ということができます。
このような現実がわかってくると、家畜とおカネの違いは歴然としていますね。わたしたちの世界のおカネには、たとえば「この一万円」と「あの一万円」には、まったく違いがない。しかし、「このウシ」と「あのウシ」をくらべてみると、性別や体重あるいは健康状態など、生物学的には同じであっても、牧畜民にとってはまったく別のもの、別の意味をもつものであることは、こうした説明からわかってもらえると思います。「このウシ」と「あのウシ」とを置き換えることができないのは、「この人」を「あの人」で代替できないのと同じです。
こういう社会に今、どんどんおカネが入ってきている、それもすごい勢いで入ってきています。わたしがケニアで調査を始めたのは1978年ですが、もちろんそのころにも人びとはおカネを使っていました。けれども、いまではその流通量がとても大きくなっているし、人びとは昔よりもすごくおカネを使うようになった。人びとはむかしから、おカネが必要になれば家畜を売っていたのですが、この35年ぐらいのあいだに、その頻度は、とても高くなってきました。また、むかしは家畜と鉄製品、あるいは家畜と農産物を直接に交換していたのですが、いまでは、それはおカネを使って買うようになっています。
そうなると、牧畜社会では、いままでは家畜が「交換媒体」や「財産」という役割を果たしていたわけですが、そうした役割が、だんだん、おカネによって担われるようになってきます。しかし、この移行はそう簡単にはいかない。たとえば、結婚のときに支払う婚資ですが、これは、いまでも必ず家畜でなければいけない。ウシ一頭は、およそ○○ケニア・シリングというように、家畜の価値はおカネに換算できるのですが、それでも、換算したおカネでは払えない。それから、そもそも財産としての家畜は、家族全体で世話をしていますから、家族みんながそれなりに権利をもっていて、だれかが勝手に売ったりすることはできないのですが、おカネの場合は、ひとりひとりが独断でだれかにあげたり、何かを買ったりしてもいい。
I:なんでもおカネに換算することができるわけではないんですね。
太田:そうです。日本でも、どの一枚の一万円も同じ価値だけれど、何かのお祝いに、のし袋にいれるおカネは、しわのない新札を選んだりしますね。おカネは、たんに価格を指示する記号ではなくて、ほかにもいろんな意味をもっている。この激動の時代に、牧畜社会で家畜とおカネがどのように使われていくのか、これがわたしの研究テーマのひとつです。
I:よくわかりました。それでは、もうひとつの研究テーマについて、教えてください。
太田:もうひとつのテーマは、アフリカの紛争と共生の問題です。このテーマについては、日本学術振興会から研究資金を受けて、いま、2011~2015年の5年間の研究プロジェクトを実施しています(URL: http://www.africapotential.africa.kyoto-u.ac.jp/)。
わたしがこのテーマに出会ったのは、まったく偶然といってもいい出来事からです。わたしは1978年から北ケニアのトゥルカナという人びとのあいだで調査を続けてきたのですが、1992年に、わたしがお世話になっていた村のとなりに、急に難民キャンプができたのです。それは本当に大事件でした。トゥルカナの地域は、ケニアのなかでもへんぴなところなのですが、ここに突然に、スーダンやソマリア、エチオピアなどからたくさんの難民がやってきて、一番多いときには、9万人を超える難民が住んでいたんです。その難民キャンプは、いま(2012年12月)もまだ、そこにあります。
I:どうして突然に、そんなところに難民キャンプができたのですか。
太田:まず、1991年の1月にケニアの隣国のソマリアでクーデターがおきて、たくさんの難民がケニアに逃げてきた。そして同じ年の5月には、こんどはエチオピアでも軍事力による政権交代があって、やはりエチオピア人がたくさんケニアに流入した。それから、スーダンでは20年以上内戦が続いていたのですが、エチオピアの前政権はスーダンの反政府軍を応援していたんだけれど、新しい政権は、エチオピア国内にいた反政府軍とその家族たちをみんな追放したので、その人たちもケニアに逃げてきた。そして1992年当時には、ケニアのあちこちにたくさんの難民キャンプがあったのだけれど、それがだんだん統合されて、いまは、カクマとダダーブという二つの地域に難民が集中しています。
I:難民キャンプができたあと、トゥルカナの人びとの生活は、どんなふうに変わりましたか。

カクマ難民キャンプのメインストリート
太田:難民キャンプといっても、それは「故郷を失った人びとが援助をうけながら暮らしている」という、ふつうのイメージとはずいぶんちがって、いわば大きな町なんですね。そこには多国籍、多言語、多民族、多宗教、多文化をもった人びと、そして、おたがいに「顔見知り」ではない人びとが集まっています。治安もかなり悪い。これだけでも都市的な状況ですよね。そして、学校や職業訓練校、病院、診療所、図書館、警察などの公共施設があるし、キリスト教会やイスラム教のモスクとか、多目的センターとかもある。そして、難民たちは自分でいろんな商売をしている。難民キャンプの中心街にいけば、レストランやバー、雑貨屋、肉屋、映画館、そしてコンピュータ学校だってあるし、国際電話だってかけられるんです。
I:国際電話もかけられるんですか!

カクマ難民キャンプのなかにある
コンピューター学校
太田:そう、予想外でしょう。衛星通信をつかっているんです。そして、難民キャンプには大量のお金と物資がはいってくる。UNHCRや国際NGOなど、たくさんの支援組織がやってきて、救援物資をとどけている。食糧だけではなくて、家の屋根をおおうためのビニールシートやテント、鍋や食器、毛布、水くみ用のジェリカンとか…。そして、おカネも物資も、地元社会に流れ出ていくし、地元の人びとは、難民の商売のために雇われたり、地元の子どもが難民の家で掃除や洗濯、水くみといった家事をしていたりする。カクマの難民キャンプは、その周囲の半径200キロメートルぐらいの範囲で、もっともたくさんの人口が集中していて、もっとも活発な経済活動がおこなわれている場所なんです。そんな大都会が、牧畜民が住んでいた半砂漠のなかに、忽然として登場したわけです。地元の人びとにとっては、それこそ青天の霹靂(へきれき)です。そして、難民キャンプといっても、周囲が柵でかこまれているわけではなくて、地元の人びとは自由に出入りすることができます。
さっきも言ったように、わたしは1978年以来、この地域の人びととずっとつきあってきたわけですが、この地元の人びとの生活が、難民キャンプからいったいどんな影響をうけるのか、難民とのあいだにどんな関係をつくっていくのかを調査しました。その内容を話すと長くなるのですが、トゥルカナの人びとは、家畜やミルク、薪や炭、家の建材などを難民キャンプに売りにいきます。難民の家畜をあずかって面倒をみている人も出てきました。こうした関係の特徴は、難民と地元民が「顔の見える」関係、個人的な親しい関係をつくっているという点です。たとえば、ミルクや薪を難民に売りに行く地元民は、いつも、同じ相手のところに届けたりしていて、単なる商売をしているのではなく、両者がお互いに助け合う関係がつくられています。
I:個人的な親しい関係が築かれているのは、驚きですね。
太田:はい。ただし、難民と地元民のあいだには、けんかや殺人といったように、暴力的な事件もおこりました。でも、同時に人びとは、個人のあいだに緊密な関係をつくりあげていますし、その関係は、難民と地元民の両方にとって、生活してゆくうえで、なくてはならないものになっていったんです。
アフリカではよく、民族間の対立が紛争のタネになっているように言われますね。文化や道徳、価値観が異なる人びとは、なかなかうまく共存していけない、というイメージがあります。でも、わたしは、難民と地元民が、お互いを隔てている壁をのりこえて、共生的な関係を自生的につくりあげてゆくプロセスを見てきました。それは、個々人が相手に対してねばりづよく、あきらめずに働きかけ続ける能力に支えられています。人間には、こうしたポジティブな関係を主体的につくりあげる能力があるということに、わたしはいつも驚かされてきました。
I:それが、いま実施されている「アフリカの紛争と共生」の研究プロジェクトにつながっているんですね。
太田:そのとおりです。アフリカではとくに1990年代になってから各地で内戦や地域紛争、民族紛争がおこりました。いまは少し落ち着いてきましたが、こうした紛争によって膨大な数の人びとが難民や国内避難民になって、困難な生活をおくってきました。そして、こうした事態に対処するために、国連をはじめとする国際社会やNPOなどの市民社会は、停戦の実現やその後の制度の構築、選挙の実施と民主化などをめざして、さまざまな支援をおこなってきました。けれども、紛争の当事者たちが和解して、引き裂かれた社会関係を修復し、共存する生活を取り戻すためには、外部からの介入だけでは、十分ではありません。
アフリカには、いま、わたしの調査地での難民と地元民との関係についてお話ししたように、人びとが自生的に共生関係をつくりあげる力があります。むかしから人びとは、いろんな知識や制度を編み出し、それ運用することで争いを未然に防いだり、解決したりしてきたわけです。こうした知識や制度をもう一度みなおして、現在の紛争処理や社会秩序の再生のために活用する方法を考える――それが、いまやっている研究プロジェクトの目的です。
I:フィールドの写真をみせていただけませんか?

自分の「お気に入り」の去勢牛の横に立つ
トゥルカナの男性
太田:牧畜社会の話をするんだったらこれがいいかなぁ(写真:自分の「お気に入り」の去勢牛の横に立つトゥルカナの男性)。このウシは横に立っている男性のものです。東アフリカの牧畜社会では、ウシとひととの「アイデンティフィケーション」(同一視)っていう現象があるんだけど、「同一視」っていったらちょっとオーバーですが、男性と去勢ウシとのあいだに、特別なつながりをみる文化がある。それぞれの男性は「自分の色」ってものをもっていて、その色をしたウシをえらんで、特別な関係をつくるのです。この男性の場合は、白と黒の斑点模様が「自分の色」なんです。彼は、この体色をあらわす単語をつかった名前をもっています。たとえば「水玉模様」とか、まわりの人から、その名前で呼ばれるようになります。それから写真のウシの角は、両方とも下に垂れ下がっていますが、人工的にこういうかたちをつくりだします。
I:おもしろいですね!
太田:彼は、みんなが集まってダンスをするときには、両腕で、このウシの角のかたちをつくって踊ります。いかにも、このウシになったかのようにね。そしてまた、このウシについての歌を作曲して、みんなのまえで歌います。ひとりの人は自分の歌を何曲ももっていて、その歌にはいろんな比喩的な表現が使われるのですが、たとえば、「白く乾ききった大地に雨が降る」といって、ウシの模様を比喩的に表現したり…。その歌のなかで男性は、自分のウシに呼びかけるのですが、彼は、ウシの体色からとった名前をもっているから、歌のなかで言及されているのがウシなのか、彼自身なのか、ウシがすばらしいといっているのか、自分をほめているのかが渾然一体となってくる。
そしてすごいなー、と思うのは、そうした歌を周囲の人びともよく知っていて、彼が自分でつくった歌を歌うとき、そうした歌にはソロ・パートと合唱のパートがあるんですが、まわりの人びとが、みんなで合唱のパートをもりあげる。夜にたき火を囲んで、そういう歌を歌っているとき、ひとりの男性のナルシシズムを、まわりのみんなが支えている、ひとりで悦に入っているわけじゃない、みんなが加勢して彼をサポートしている、ここがすばらしいところなんです。
I:太田さんもご自身の歌をお持ちなのですか?
太田:ううーん、まぁ、はい(笑)。
I:どういう内容なんですか?
太田:ダメダメ(笑)歌わないぞ。
I:こんどゼミで歌ってくださいね。それでは、アフリカ専攻の特徴について教えてください。また、受験生に対するアドバイスもお願いします。
太田:アフリカ専攻には14人の教員がいて、それぞれに専門分野や調査地域がちがうのですが、多くの教員は、大学院生に対して「これこれの研究をしなさい」というようにテーマを与えることはしません。学生がどんな研究をやっても、やめなさいとはあまり言わない。その意味で学生はすごく自由なんですが、逆に、自由だということは、自分で責任をもたないといけないことにもなるので、厳しい環境だともいえます。自由は尊重される、しかし自由には痛みがともなうこともある、ってことですね。
大学院に入学したら、学生のみなさんには、悩みながら自分で研究をくみたててほしいと思います。教員が「これこれをテーマにしたら、こんなことがわかるはずだから、おもしろいよ、やってみる?」というように、学生に研究テーマを示す、ということもあります。学生にとっては、教員にそう言ってもらうことが楽なときもあります。けれども、それでは、すでに答えがわかっている問題にとりくむみたいなものですから、わたしはあまりおもしろいと思いません。学生が自分で見つけた研究テーマを深めていって、教員が知らないことを教えてくれる――学生がそのように育ってゆくことを教員は期待しています。研究者どうしとおなじですね。
I:どのような学生さんをもとめていますか?
太田:どんな人でも、アフリカについての研究がしたいなら大歓迎!そういう人はみんな同志だと思っています。
I:もう少し、具体的に(笑)。
太田:これはアフリカ研究に限らず、研究一般にあてはまることですが、ねばりづよく、ひとつのテーマを追いかけることが大事だと思います。研究の成果は、どこかにころがっているものではありません。どこかに埋まっているダイヤモンドを掘り出してくる――研究は、そのようなものではありません。では、どういうものかというと、自分が拾ったものがダイヤモンドではなくて、単なる石ころだったとする。みんながそれを「つまらん」と言うかもしれない。けれども、その石を一所懸命みがく作業を積み重ねていくと、それがだんだんダイヤモンドになっていく、その「磨く作業」をねばりづよく続けること、これが大事です。教員は、学生がそうした作業をするためのお手伝いをしますが、ときには孤独に耐えながら(笑)、熱意をもって作業にとりくむ――教員もじつは同じことをしているのです。そういう意味でも同志ですね。
I:入学するまえに、こういうことしておくといいよっていうアドバイスはありますか?たとえば太田さんがご自身を振り返ってみて、こういうのが役に立ったなぁ、とか…。
太田:わたしは、大学院に入学するまえ、つまり学部学生の時代には、そうとうにサボりの学生でした。とくに、1回生、2回生のときはほとんど授業にもでなかった。まぁ、そういう時代でもあったのだけれど。
I:じゃあ、勉強せずに、なにをなさってたんですか?……飲んだくれ?
太田:うーん、それはちょっとおいとくとして…(笑)。いまから思えば、学部学生の時代に、「研究するって、なにか、自分が知らないスゴイ世界なんだな~」と思ったことが、あとで役に立った気がします。大学1年生のときに英語の先生が最初の授業で「みなさんが読みたいと思うものをテキストにしましょう、何がいいですか」って学生に聞いたので、わたしと何人かの仲間が「ビートルズ!」と言い出して、それが採用されたんです。そして、いきがかり上、わたしたちはビートルズのレコードの歌詞カードをコピーして、みんなの教材を用意することになったのだけれど、その先生がすごい人でした。お名前を忘れてしまったのだけれど(笑)。
I:どんなふうにすごかったのですか?
太田:高校のときの授業とは、まったくちがった世界があった。英語の説明をしていても、話はそこで終わらない。いまから思えば、あの先生は社会言語学みたいなことを話していたのだと思う。その言葉をつかっている人たちの地域や文化、階級とかと言語との関係とか、言語を使うことをコミュニケーションという側面から見るとか、そういったことだったと思います。その先生の話を聞いていて「この人はすごい!」って、思った。話している内容を自分でもすごく楽しんでいるし、その内容がとても深いように思えたし、それを相手に伝えるちからもすごい。そのときにわたしは、「こんな人には、いままでに会ったことがない」「研究って、自分が知らなかった世界なんだ」と思った。しかし、その世界の一端は感じることができました。
I:それは幸せな出会いでしたね。
太田:うん、でも、残念なことに、わたしはその先生とは、その後に接点がなかった。そのあと、もうひとり、すごい人に会いました。それは、伊谷純一郎さんっていう人でわたしが大学院生のときに指導教員だったひとです。この人が日本の霊長類学を創始した人のひとりだってことは、知っていますね。
I:はい、聞いたことがあります。
太田:わたしが学部時代の2年生のときに、この先生の「自然人類学」っていう授業を受けたことがあったのですが、これが面白かった。伊谷さんの授業は、たぶん、研究の最先端のことを話していたのだと思う。内容はよくわからなかった。「概論」みたいな説明がほとんどない授業だったんです。相手は学部の1年生や2年生、つまり、しろうとを相手にしているのに、不親切な授業でした(笑)。でも、どうしてなのかわからないけれど、その授業がおもしろかった。世界の研究者を相手にして、それと競争している最前線の研究の現場の熱気みたいなものが伝わってきました。
この先生には、わたしは、ある日の授業がおわったあとで教壇を去ろうとするところをつかまえて、「自然人類学を勉強するためには、どんな本を読んだらいいですか」ってたずねたんです。そんなことをわたしがしたのは、あとにも先にも、このときしかなかった。そしたらその答えがまた、伊谷さんらしかった。トーマス・ハックスリーの「自然における人間の位置」っていう本を薦めてくれたのだけれど、「翻訳はだめだから英語で読みなさい」というんです。
I:えー、翻訳が出版されているのに原書を読めってことですね。
太田:そう、まいっちゃったな、これ。さっきも言ったけど、相手はしろうとですよ(笑)。わたしは結局、原書は読みませんでした。いまでも読んでいない(笑)。まあ、それはともかく、さっき言った英語の先生とか、伊谷さんとか、大学にはすごい人がいるので、残念ながらわたしはちがうけれど(笑)、そういうすごい人に出会って、研究の奥深さをそこはかとなく感じておく、大学生にはこういう経験をする機会がたくさんありますので、是非、利用するといいと思います。
I:では、将来、一緒に研究するかもしれないみなさんに、最後にしめのなにか、かっこいいひとことを…。
太田:受験生にひとことね、むずかしいねー。さっきも言いましたが、うちの研究科では研究の同志を募集中です。是非、ASAFASに来てください。一緒におもしろいことをやりましょう!