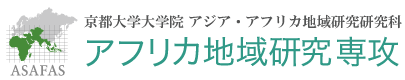*インタビュアー:A
A:本日は、よろしくお願いします。安岡さんは本研究科のOBですが、そもそもどのような経緯で、ASAFASに入学したのですか?
安岡:学部はうちの大学の理学部でした。ASAFASのアフリカ専攻の母体になったのは1986年にできたアフリカ地域研究センターで、センター設立時のスタッフである伊谷純一郎先生や市川光雄先生は、理学部の人類学講座から移ってきました。また、それ以降に着任したスタッフのなかにも理学部出身の人が多くいます。
ぼくは1995年に大学に入学して、紆余曲折して学部4回生の課題研究で自然人類学を選び、ニホンザルの大腿骨の断面を計測したりしていました。それで、そろそろ院試の勉強をしようかと思って過去問を見ていると、「生態人類学」という名前が目に入りました。しかし当時は、生態人類学という分野は理学部にありませんでした。そこで調べてみると、「アフリカセンター」という部局があることがわかりました。ぼくの5つくらい上の学年までは「アフリカセンター」の院生の一部は理学部に所属していたんですね。また、どうやらアジア・アフリカ地域研究研究科というのができたばかりだ、ということもわかりました。それで、そのまま理学研究科か、ASAFASか、という選択肢になって、結局、ASAFASにしました。アフリカそのものにものすごく興味があったからASAFASを選んだ、というわけではなかったけどね。
A:ええ! そうなんですか!?
安岡:うーん、なんとしてもアフリカに行きたいとか、そういうわけではぜんぜんなくて、どちらかというと、フィールドワークをして、生態人類学をやりたい、というところに重心がありました。どうしてそうなったかというのを、もうすこしさかのぼって話しましょうか。もともと大学に入学したときは、理学部の多くの新入生がそうだと思うけど、数学か物理学をやろうと思っていました。ぼくは田舎生まれだし、親戚に大学教授とかがいたわけでもないから、京大をはじめとする「大学」というものにある種の幻想をもっていて、物理学者のリチャード・ファイマンみたいな教授がいて、すごく面白い講義をしているんじゃないかと期待してました。でも、ぜんぜんそんなことなかったね。それで、あーこんなもんかと思って、あまり講義に出なくなって、1、2回生のころは、わりとまじめにサッカーをやってました。
それで、3回生になるころ、そろそろ将来のことを考えようかという気分になってきました。といっても、やりたい職業は研究者一択でした。高校の進路相談で、担任の先生に「おまえはサラリーマンとか、公務員とかは絶対に無理」と言われたくらいでしたしね。でも、いまさら数学とか物理をやるのは厳しいかなと思ってたし、同級生には、数学オリンピックでメダルを取った人とかいたし、そもそも若くして活躍する分野だから、2年も遊んでたら生き残るのは無理やろな、と思いました。さいわいにも理学部は入学時に専攻を決める必要はなくて、3回生のときに選ぶようになっていました。それで、ちょっと遅れて参入しても勝負できる分野がいいなと思って、フィールドワークをやるような分野だったら、もともと時間がかかるし、若いころにすごい実績がなくても、なんとかやれるんじゃないかというのもあって、それで生物学とか地質学の実習をとったりして、4回生になるときに生物系の人類学を選択したわけです。古人類の化石を掘ったりするところですね。
A:ガラっと変わったんですね。
安岡:まあ、もちろん、もともと生態学とか古生物学にも興味があったんで、ぜんぜん選択肢になかったというわけではないけど。中学生のときにマイケル・クライトンの『ジュラシック・パーク』という小説を読んで、古生物学とバイオテクノロジーと、あと複雑系科学なんかがからみあいながら、生物の進化や自然界における人間の位置について議論されているところに興奮してましたし。映画にもなりましたね。小説のほうがおすすめですが。
でも、結局、さっき話したように理学研究科ではなくASAFASを選びました。その理由というか…、理学部にいてちょっと違うな、と感じたところがあって、それは理学部の研究は専門性が強すぎるというところですね。サイエンスの最先端を走るためには、やはり自分の専門に特化して、そのなかで凌ぎを削る必要がある。もちろん、それぞれの専門については、それぞれにおもしろいのですが、じっさいにそのなかから自分の専門をひとつ選んで、これからずっとその専門のなかで研究をつづけるという事態を、なかなか想像できませんでした。それよりも、いろんな学問分野を横断しながら、人類、世界、そして宇宙の真理を解き明かしたい、そういった野望があったわけです。
アジアではなくアフリカを選んだのは、はじめに話したように、自分と多少とも類似した経緯でアフリカ研究をはじめたらしいスタッフが何人かいたことが、けっこう大きいですね。それで、スタッフの書いた本をいくつか読んでみると、『生態人類学を学ぶ人のために』の序論だったと思いますが、「生態人類学は大学院からはじめてもOKだし、むしろそのほうが好ましい」というようなことを、後に指導教員になっていただいた市川さんが書いていて、「ここしかない!」と思いました。
A:フィールドはどのように決めたのでしょうか。
安岡:市川さんと話して、とりあえず博士予備論文は日本でやったらどうや、ということになりました。ぼくより上の世代のアフリカ研究者は、修士のときは日本で調査した人がわりと多かったし。でも、理学研究科なんかだと地域の縛りはないけれども、ASAFASだとさすがに「アフリカ地域研究専攻」なのに日本をフィールドにするのはどうなの、という話も出てきますし、最近は、みんな最初からアフリカに行くみたいですね。いずれにしても、大学院からフィールドワークに入門したぼくにとっては、いい選択でした。
で、どんなテーマでやるんや、という話になって、平等社会のなりたちとか、人間と動物の関係とかに興味があります、などとざっくりとした話をすると、市川さんが、たぶん思いつきで「猿害はどうや」とおっしゃりまして、じゃあとりあえずやってみようかと思って、自己紹介ゼミのときに「猿害」をやりますと発表しました。そしたら、入学してすぐの5月にあったアフリカ学会で、先輩の飯田卓さん(現・国立民族学博物館)から、当時、弘前大学にいた今井一郎さん(現・関西学院大学)を紹介していただきまして、お話を聞いたところ、猿害の研究費をもってて調査する人を探している、ということでした。それで、ふたつ返事で行きますと答えました。というわけで、青森の津軽地方でフィールドワークをはじめました。でも、この予備論の時期は、ぼくの人生で最大の危機でしたね。
A:危機ですか?
安岡:あまり人づきあいが得意じゃなかったんですが、フィールドの人びととのつきあいは、大きな失敗はなく、なんとかやれました。でも、京都に帰ってきて報告したゼミでは、ぼくのアイデアがまったく伝わらなくて、愕然としました。アフリカ専攻では、伝統的に、とりあえずフィールドに行ってこい、と放り出すので、データを取る方法とか、ものごとを見る理論的枠組みとか、ぜんぶ自分で勉強するわけです。そういうのは嫌いじゃないんだけど、ぼくは自分の頭のなかで完結したら、それで満足する傾向が強かったんで、「ほら、こういうふうに理解できます」と発表しても、みんな、ぜんぜん意味がわからないわけです。たとえば、今ふりかえると笑っちゃうんだけど、「猿害の免疫系モデル」という発表をしたりしました。当然ながら、ぼくは、猿害の全貌を把握するためにすごく有効なモデルだと思って発表したんですが、「じゃあ、リンゴが赤血球で、猿がマラリア原虫ということかな?」といったコメントが出たりして。
こういう経験をとおして、なんというか、人間は孤独だ、ということを身にしみて実感しました。これまで、ぼくのアイデアが他人にちゃんと伝わったことは一度もなかったんじゃないか、という可能性をつきつけられると同時に、それがほとんど事実だと思えましたね。
でも、そのうち、どうやらアイデアを表現するスキルが決定的に低いことが原因だとわかってきて、安心しました。それならスキルを磨けばいいわけです。この点では、指導教員だった市川さんには、たいへんお世話になりました。いまでは、ぼくが文章を書くときには、自動的に、頭のなかに市川さんのコメントが浮かびます。「意味がわからん!」とか「くどい!!」とか。修正案もすらすらと出てくる。それにモニタリングされながら、文章を書いているかんじですね。最近は、ようやく自分の文体ができてきて、ある文を書いたときに、これは「市川赤ペン」には直されそうだけど、でも、ここは好みの問題だから、これでええかな、といった判断ができるようになってきました。
人生最大の危機に臨んで大きく道を外さずにすんだのは、父親のアドバイスも大きかったですね。ぼくは小さいころからなんでも我流でやるのが好きだったし、じっさい、そうしてきました。たぶん小学校の高学年くらいからは、父親に助言を求めたことはなかったし、父親がぼくに何かを教示しようとしたこともなかった。塾にも行かなかったし、学校の先生の言うことなんか、ぜんぜん聞いてなかった。でも、ちょうど青森で調査をしているころ、実家に帰省していたときに、父親が、おもむろに「守破離(しゅはり)」という考え方について話しはじめました。武道とか茶道の道を極めるための知恵の話であり、また、我流の限界を諭す話ともいえますね。以前だったら「おれは守と破はスキップして、いきなり離やな」と思ったはずだけど、このときは、とりあえずこの順番どおりにやってみようか、と思いました。
それで、青森にもどりました。青森では、大学院入学後の最初の2年間のうち、最初に1か月、それから2か月の調査を3回やって、ぜんぶで7か月滞在しました。ちょうど現地の保育所が閉鎖して、そこが無料の宿舎になっていて、金銭面ではたいへん助かりました。
では、ひとつ質問だけど、このあたりではサルがリンゴ畑にやってきて被害をあたえるんですが、もちろんリンゴの実を食べられるのは痛いんだけど、それ以上に農家がいやだと思っていることはなんだと思う?
A:えぇ…? 木の根っこというか、根幹の部分をやられるというか、果実だったらその年だけだけど、もっと長期的な…
安岡:なかなかするどいね。正解は、芽を食べることですね。冬のあいだ餌が少ない時期に、枝の先についている芽を、サルが食べちゃう。芽っていうのは、花も咲くんだけど、枝もそこから伸びる。それをサルが食べると、枝の伸び方のバランスが崩れて、樹形が想定どおりにならないわけです。リンゴ栽培というのは、とくに日本のリンゴ栽培はそうだけど、大玉高品質生産といって、大きくて見栄えがよく、なおかつ、おいしいリンゴを高値で売る、というビジネスモデルです。そのようなリンゴを、いかに効率よく実らせるかがリンゴ栽培の肝なんだけど、それはいい樹形をつくることができるかどうかにかかっているわけです。だからリンゴ栽培で一番重要な作業は枝の剪定なんですね。農家の人によれば、だいたい3年くらい先の樹形をイメージしながら、剪定するそうです。でも、芽を食い散らかされると、それが台無しになる。このような話を聞いているうちに、猿害というのは、たんに山からサルが下りてきて農作物を荒らしているというだけではなく、その被害意識を大きくしている背景に、日本で特徴的な発展をとげたリンゴ栽培の技法があり、その技法の高度化をうながした高級リンゴをもとめる市場文化があることがわかってきました。このようなことを博士予備論文で書きました。

サルに冬芽を食べられて形が崩れた木

理想的な樹形
A:で、その予備論をふまえて、アフリカへ…
安岡:大きな問題意識としては、人間と動物の関係、人間と自然の関係、というのがありました。さっきも言ったように、アフリカに行きたいというより、フィールドワークをやってみたいというのが先にあったんで、絶対ココだっ、という国とか地域があったわけではないけど、森がいいかなとは思っていました。ぼくは、面積の98%くらいが森林に覆われている高知の山村で生まれ育ったんですが、ふつうに町で育った人とくらべると、何十倍も山とか川で遊んだと思います。それで中学から町に出たんですが、町の学校の友達を家に連れてきて山とか川で遊ぶと、みんなぼくの動きについてこれない。友達からは野生児だと言われていました。でも結局のところ、ふだんの生活圏は、道路沿いの2%の土地にへばりついているわけです。それにたいして、アフリカの森で生活している人たち、つまりピグミーさんたちは、森を面的に縦横に移動しながら生活している。上には上がいるということですね。
それで、予備論を書いた後の3月ころだったと思いますが、一足先にカメルーンでバカ・ピグミーの調査をはじめていた服部志帆さん(現・天理大学)のところを訪ねて帰ってきたばかりの市川さんが「君にすごくいいところが見つかった」とおっしゃるわけです。
A:安岡さんご本人が見る前に決めちゃったんですか!?
安岡:市川さんが「そこ以上にいいところは、カメルーンにはない!」と断言するからね。じゃあ、とりあえず、そこに行ってみましょうか、ということになりました。当時、DRC(コンゴ民主共和国)は戦争をしていたし、コンゴ共和国も政情不安で、アフリカの森のなかではカメルーンは数少ない選択肢のひとつでした。それで、市川さんと一緒にその村に行って、市川さんはすぐに帰って、ぼくは1年ちょっと滞在しました。
A:最初からそんなに長いこと行かれていたんですね。
安岡:日本でフィールドワークをやって、論文をひとつ書いていたからね。最近の学生は2か月くらいの予備調査をして、それから1、2回フィールドに行って、2年で予備論を書いているよね。はじめてアフリカをやって、しかも6か月くらいの調査で予備論を書くなんて、なかなか大変だろうなあと思って見ているんだけど。ぼくらのころは、ほとんどの人は1年くらいはフィールドに行って、3年かかって予備論を書いてました。今の学生は、えらい頑張っているというか、むしろ、かなり無理をしてるんじゃないかと思いますね。ともあれ、ぼくは最初の渡航で14か月滞在して、帰ってきて2か月半くらい日本にいて、また9か月カメルーンに行きました。気分的には2年ぐらいずっと行ってたかんじですね。

ヤマノイモの一種を収穫したバカ・ピグミーの女性
というわけで、やっと今の研究テーマに近い話になってきました。カメルーンのフィールドワークでなにをしてきたかというと、大きなものでは、いまのところ3つあります。一つ目は、フィールドでつきあってきたバカ・ピグミーたちは、野生のヤマノイモ類を採集して食べているんですが、それを収穫して調理するという過程そのものが、ヤマノイモの分布の拡大につながっている、ということを明らかにしてきました。この事実は、いろいろな文脈で重要な意味をもっていて、たとえば、ピグミーは熱帯雨林の先住民かどうかという問題や、野生植物のドメスティケイーションはどのようにはじまったのかという問題、また、住民参加型の森林保全をどのように計画するかという問題などに、大きな示唆をあたえてくれます。それぞれの背景を話し出すと長くなるので割愛しますが、本とか論文をいくつか書いていますので、興味があったら読んでみてください。
二つ目は、狩猟のサステイナビリティの問題です。アフリカのコンゴ盆地とか、アマゾンの熱帯雨林では、今、ブッシュミート・クライシスということが言われていて、国際的な関心事になっています。ブッシュミートというのは、アンテロープ類とかサルとか、まあ野生動物の肉ですね。それが交通網の発達とともに大量に都市部に売りに出されるようになって、野生動物の枯渇が懸念されているわけです。道路は主に伐採会社がつくります。伐採では有用な樹種だけを伐るから、森自体が消失するような大規模なものではないんだけど、その道路を使って肉を買いつける商人がやって来て、肉を売るための狩猟がどんどん活性化するわけです。じっさい、ぼくがフィールドワークをしているときに、森のキャンプで2か月半過ごして村に出てきたら、そのあいだに道路が開通していて、バーなんかもできていて、音楽がガンガンなってました。それまでは、川で隣村と隔てられていて、しかもその数年前までは40kmくらい歩かないと町までたどり着かなかったところなんですが。

木材を搬出するトラック
それで、かれらの生活が一変した。いや、「一変したように見えた」と言ったほうがいいかもしれない。最近、アフリカは大きく変化しているという話をよく聞くし、多くの地域ではそれが事実だと思うけど、カメルーン東部の森林地域の場合、ガラッと変わりかけることはたしかにあるんだけど、それが元の木阿弥になるのも早い気がします。村が大きな経済圏につながる道路ができても、メンテナンスを怠ると、木がどんどん倒れてきて、車が来なくなって、そうするとまた元の生活に戻っちゃうわけです。

狩猟した動物を販売するために燻製にする男性
ブッシュミートは、道路がつながっているときだけを見ると、これはほんとうに絶滅するかもしれない、という勢いで獲られていましたが、その後、道路が傷んできたり、取り締まりが厳しくなったりして、量的にはかなり抑えられています。しかし、いったん法律やら規則やらができてしまうと、もともと自給的にやっていた狩猟とか、生活必需品の購入のための肉の売り買いとか、そういったものも違反になってしまいます。じゃあどうすればいいのか、というのが目下の課題ですね。理論的にも実践的にもセンシティブなところなんで表現が難しいんだけど、住民の動物に関する知識と科学的な知識を組み合わせて、両者が対等なかたちで協働しながら狩猟をマネジメントできる仕組みをつくれたらいいなと思っています。
三つ目は、ゾウやカワイノシシの肉を、仕留めたハンター自身は食べることができない、というバカ・ピグミーのルールの謎を解き明かすことをとおして、狩猟採集社会の特徴とされている平等主義や食物のシェアリングの理解を深めようとする研究です。なぜこの話がおもしろいかということを説明すると長くなるのですが、簡単に言うと、まず、大人どうしで日常的に食物をやりとりするのは、あらゆる動物のなかで人間だけ、ということがあります。それで、狩猟採集民にみられるシェアリングは、その基底的なやりとりのひとつだと考えられるわけです。また、かれらは「われわれはみな平等な存在である」というある種のイデオロギーにもとづいてシェアリングをしているわけではない。おそらく、さっき言ったような、過剰性をもつルールがわざわざ設けられているところが肝ではないかと思うわけです。それで、いろいろ調べてみると、どうやらこのルールには、森の精霊の観念が関与しているらしい。つまり、狩猟やそれにともなう肉のやりとりは、人間と動物のあいだ、人間と人間のあいだ、という現実に存在する者どうしの関係にとどまらず、精霊という観念的なものが関与している。もっと一般化すると、このような「想像されたもの」が発明されたとき、言いかえると、脳の大型化のある段階でそれが可能になったときに、人類は日常的な食物のやりとりを円滑にできるようになったのではないか、というようなことを考えています。
A:すごく盛りだくさんの博士論文だったんですね。
安岡: いや、博論の大部分は最初に話したヤマノイモ関連の内容だけでした。幸運にも、わりと早く就職が決まったんで、そのときまでに書いていた論文をまとめて博論にして提出しました。公聴会も大学での仕事がはじまってすぐの5月だったし、講義の準備とも重なって、かなりドタバタでした。まあ、ずるずる先延ばしになるよりいいかなと思って。
A:初めてフィールドに行ったときと最近のフィールドと比較して、変化はありますか。
安岡: ぼくの調査地は、ほとんど変わっていません。もちろん、細かいところではいろいろ変わっているけど。たとえば、LEDのヘッドランプが普及してきたとか、裸足じゃなくてビーチサンダルを履く人が多くなったとか。はじめて行ってから15年ぐらい経つけど、その程度の変化しかない。といっても、点と点で見るとそうだけど、さっき言った道路のように、そのあいだにいろいろと紆余曲折はあったわけです。たとえば、村から5kmくらい離れたところに古いカカオ畑とかコーヒー畑があります。どうしてかというと、何十年か前には、コナベンべという、ピグミーとは違う民族の農耕民が調査村にたくさん住んでいて、カカオなど栽培して売っていたんですね。でも、1970年代に農民たちがもっと便利な地域に移住してしまい、それらの生産も廃れてしまったわけです。
A:学校や病院が必要になったとかいう、そういう変化もないんでしょうか。
安岡:調査村には学校はないね。以前にはあったようだけど、ぼくが行ったときには、もうなくなってました。この辺の学校が存続するかどうかは、教師を確保できるかどうかによります。町から教師が派遣されてくるんだけど、その人が病気になって帰ってしまったり、死んじゃったりしたら、そのあと補充されないことが多い。もちろん、町に近いところだと事情は違うと思いますが。また、調査村から一番近い医者は、70~80kmくらい離れた村にいるかな。交通の便も悪いので、ピグミーさんの場合、病気になっても病院に行くことはまずありません。ほんとうに死にそうになって、はじめて農耕民の村長が車を手配したりして、すでに手遅れだったということもあったようです。
A:私、アフリカはどんどん変わっていっているんだと思っていました。カメルーンの他の地域とも違うんでしょうか。
安岡:カメルーンの西部の方は道路がよく整備されていて、舗装道路が網目のように走っていますね。でも、東部の森林地域では舗装道路が整備されはじめたのはわりと最近で、すこしずつ伸びてようやく州都ベルトアまでつながりましたが、まだ県庁のある町ヨカドゥマまでは達していません。もちろん、未舗装の自動車道路はありますが、メンテナンスが大変で、雨が降ったら低いところが水没したり、坂道のまんなかに巨大な溝ができたりするし、強風で木が倒れたら重機で撤去しないといけないこともあります。
おなじ狩猟採集民でも、南部アフリカの乾燥地に住んでいるブッシュマンの社会は、ここ数十年で大きく変化していますが、ピグミーは、そのような変化から、まだすこし距離があります。それにはいろいろな要因があるでしょうが、道路のメンテナンスの大変さに現れるような気候の違いも大きいと思います。乾燥地域には熱帯雨林とは違った気候の厳しさがありますが、いったん道路を作っちゃうとメンテナンスが比較的容易だという点では、外部からの影響は累積しやすいんじゃないでしょうか。それにたいして、熱帯雨林は、外部の影響をどんどん掘り崩していくようなイメージですね。
A:それでは、アフリカ専攻の特徴はなんでしょうか。
安岡:ぼくは、学生として7年半ここにいて、それから9年くらい別の大学で働いて、つい最近になって教員として帰ってきたところなんで、学生の立場からの話になりますが、ぼくがASAFASに入学して、すごく新鮮で、刺激的だったのは、人文・社会系の学部から来た人たちといろいろ議論できたことでした。それには同級生だけではなくて、先輩とか後輩もふくまれます。
A:入りたてのときに違いを感じたりしましたか。
安岡:ぼくは学部時代の友人もみんな理・工・農だったから、人文・社会系の人の考え方は、すごく異質でしたね。でも、よく議論しました。そのときは、ひとまず自分の出自に優位性がある、という立場から話すわけです。それぞれ自分がかつて選んだ学部を卒業してきたわけだから、そこでの考え方にシンパシーがある。ぼくだったら、理学部的なところに自分の立ち位置がありました。だけど、そのまま大学院に行かずにASAFASに来たということは、そのような既存学部にどこか違和感をもっているわけです。そんなアンヴィバレント(両義的)なところがあって、とりあえず出身学部的なところに立つけど、一方で、相手の考え方についても、そういうのもありかなと思いながら議論することになります。そういうのをくりかえすうちに、自分の立ち位置が変わってきたというか、考え方の幅が広くなってきましたね。
それで、もともといた理学部の友人と話す機会があると、彼の考え方になつかしさを覚えて、こんどASAFASの同期をこの論理でやりこめてやろう、などと考えながら、でも、その場では、どういうわけか文系的な立場から話したりするわけです。イソップ童話に「卑怯なコウモリ」という話がありますが、その逆バージョンですかね。このように、相手と自分の立ち位置を両睨みして、自分の立場を調節しながら話すことは、フィールドワークでも必要なことだし、論文を書くうえでも重要なことだと思うんだけど、そういう意味でも、いろいろな出自をもつASAFASの先輩・同輩・後輩と議論できたことは、すごくいい経験でした。
A:ここに来ようと思っている学生さんに求められているものや、学部時代にしておいたほうがいいことはありますか。
安岡:ぼくが高校生くらいのころまで「アメリカ横断ウルトラクイズ」ていう番組があって、欠かさず見ていました。大学に入ったら出場するつもりでしたが、残念ながら高校のときに番組が終わってしまいました。それはともかく、このクイズのキャッチフレーズが「知力・体力・時の運」だったんですね。これはフィールドワークにも当てはまると、ぼくは思っています。フィールドワークは、研究という知的営為の一部なので、「知力」が大事なのは当然そうだけど、「体力」も非常に大事です。その体力には二つの意味があって、第一に、ぜんぜん違う環境に住んでいる人たちと一緒に長期間生活するうえでは、持久力とか、環境適応力とか、病気に強いとか、身体的な強靭さという意味での体力があることはアドバンテージになります。
第二に、身体をとおして人びとの生活感覚を理解するという意味での体力ですね。生態人類学では、数値化されたデータをきちんととることが重視されますが、かならずしも統計処理のために数値データを重視しているわけではない。むしろ、身体をつかって得られた理解を凝縮して表現する手段として数値化が重視されているというところがあると思っています。この数値化の過程を身体をつかって経験しておくと、他の研究者のデータを読んでも、そのデータの背後にある生活感覚をおおよそイメージできるようになります。もちろん、数値データに頼らなくてもそれができることもあるでしょうが、有力な方法のひとつだということです。
A:「時の運」というのは?
安岡:さっき言ったように、ぼくの博論の大部分は、バカ・ピグミーたちのヤマノイモの利用についてだったんだけど、このテーマになったのは、まったくの偶然でした。ぼくが調査をはじめた年に、かれらはヤマノイモをたくさん収穫して食べる森でのキャンプ生活をしたんですが、次の年はやらなかったし、前の年もやらなかった。また、ゾウ肉のルールの話にしても、ぼくがいるあいだに伐採道路が開通して、商人が鉄砲をもって来て、ゾウ狩りが盛んになったんだけど、2、3年遅ければ狩猟の取り締まりが厳しくなってましたので、ゾウ狩りに同行することはできなかっただろうし、話を聞くことも難しかったと思います。じっさいのところ、フィールドワークというのは、フィールドでたまたま遭遇した出来事のなかに研究テーマを見つけて、それに食らいついてデータをとって論文を書くのですが、後から振り返ってみると「ああ、運がよかったな」と思えるわけです。
それはもう、ほんとうに運がよかっただけかもしない。でも、そうではなくて、運というのはどこにでも転がっていて、それをつかむことができるかどうかは、こちら側の問題かもしれない。たとえば、フィールドワークの入門書に「テーマはそこらじゅうに転がっている」とか書いてあったりするけど、これは後者の立場ですね。
これと関連して、なるほどと思った話があります。高校の同窓会が何年か前にあって、そこである会社の社長をしている大先輩の講演がありました。その話のなかで、人から「運がよかったね」と言われるようになれ、とその社長さんはおっしゃりました。そのためには、忍耐力と判断力が必要だと。忍耐力というのは、チャンスが来るまでコツコツと地道な鍛錬をつづけて基礎を確立するちから。判断力というのは、何かが起きたとき、それをチャンスだと認識して、大胆に行動するちから。このふたつがないと、人から「運がよかったね」と言われるようなことは成し遂げられないというわけです。
この方はかなり有名な会社の社長さんですから、人から羨まれるような大きな運をつかんだのだと思います。ぼくも、さっき言ったように、自分では「運がよかった」と思っていますけど。重要なのは、それがたんなるラッキーだったとしても、それで片付けてしまわずに、うまくいった要因、ときには失敗した要因をきちんと反省して、忍耐づよく基礎を固めつつ、よりよい判断ができるセンスを磨いて、もっともっと「運のいい人」になるよう精進することですね。それがフィールドワークの本質のような気がします。
A:深いですね。
安岡:あと、入学した学生さんに期待しているというか、楽しんでほしいことがもうひとつあります。誰でも高校とか大学での勉強のなかで得意な分野があると思うんだけど、たとえば、1を聞いたら、10とは言わないまでも、3、4くらいは理解できる分野もあれば、1を理解するのもたいへんな分野があると思います。たぶん多くの人は、学部に入るときは前者を選んだでしょう。でも大学院で研究をするさいには、自分が得意でない分野に越境してみることが、すごく大事だと思います。
すごく個人的な話なんですが、ぼくは小学生のときソフトボールをやっていて、中学からサッカーをはじめました。ご存知のとおり、まったく違うスポーツです。中学のチームメートはみんな小学生のときからサッカーをしていて、ぼくなんか足技は下手くそで話にならないわけです。でも、ある程度なれてくると、ぼくがみんなを圧倒できる領域があることがわかってきました。浮き球にたいする第一歩が誰よりも速かったんですね。じっさい、ボールが蹴られた瞬間に、落ちてくる場所がわかりました。サイドから放り込まれたボールにちょこんと触ってゴールに流し込むとか、コーナーキックに合わせるとか、そういったところに自分の仕事場を見つけたわけです。この能力は、間違いなく、ソフトボールでセンターの守備を練習することをとおして身についていたのだと思います。
このような越境の効用は、学問分野のあいだでもあると思います。じっさい、ぼく自身、理学部からASAFASに進学したときには、ソフトボールからサッカーに転向した経験をある種のロールモデルとして、成功を信じていましたしね。異なる分野に越境していくと、常識的な知識がなくて恥をかいたり、なかなか馴染めない考え方があったりするけど、地道に基礎を固めていくと、バッと開ける瞬間があります。もともと得意だった分野の考え方だったり、知識だったりが、急に活きるようになってきて、その道一本の専門家にはない味が出てくるわけです。一方で、自分の得意分野にも幅が出てくる。このような越境をたくさん試みることで、独自の組み合わせ、味つけの妙みたいなものをつくりあげていくことが、学際領域である地域研究の醍醐味ではないでしょうか。
A:学部のときはぜんぜん違う学問をしていた人でも、フィールドワークとかしたことなかった人でも、ここに来たら…
安岡:「知力・体力・時の運」のどれかに自信のある人、なかでも、なんとなく「自分は運がいいんじゃないか」と思っているあなた。大歓迎です。もちろん、学部で学んだことの延長にある研究をしたいという人も大歓迎ですし、そうでなくても大歓迎です。